こんにちは! パドルです
今日は最近読んだミステリー小説の「たかが殺人じゃないか」を紹介します
こちら辻真先による小説で、2021年の「このミステリーがすごい」第1位の作品です
舞台は昭和24年(1949年)の名古屋で、主人公は男子高校生の勝利(かつとし)です
彼はミステリー小説作家になることを夢見ています
「たかが殺人じゃないか」も、勝利が書いた小説という設定です
こんな人におすすめ
この小説はこんな人におすすめです
- 最後に「ああ、そういうことだったのか…!」と思いたい
- ミステリーが好き
- 戦後間もない時代の学生生活がどんなものだったか興味がある
当時は終戦してから間もなく、GHQ主導のもと、それまで日本で当たり前とされてきたことを無理やり変えさせられていた時期でした
学校制度もその一つです
戦時中までは高校で男女共学というものは存在せず、学校が再編成されてこの年に初めて共学になります
勝利は高校三年生ですが、今まで男子校に通っていたものがいきなり共学に通うことになり、女生徒にどう接したらよいかわからない状態です
私自身も中高と男子校だったので、勝利の気持ちは痛いほどわかります
そもそも内向的な性格なこともあり、大学に入ってからのコミュニケーションには苦労しました
(正直今も苦労はしてますが…)
この時代背景は直接物語中のミステリーとは絡まないのですが、この時代だからこそ起こる出来事の描写もあって勉強になりました
あらすじ
物語のあらすじを簡単に紹介します
勝利はミステリー好きで推理研究部の部長です
推理研究部は部員が少なく、映像研究部と同じ部室で活動しています
それでも全員合わせて5人しかいません
夏休み中、部員5人と顧問の操先生(あだなは巴御前)とで合宿をすることになりました
その合宿の途中、ある家の近くで巴先生が腐臭に気が付きます
みんなで家の中を覗いてみると、とある男性の死体がありました
すぐに死体に近づこうとしますが、家の入口はすべて塞がれていました
そう、密室だったのです
その事件の解決は警察に任せることになったのですが、数か月後に第二の事件が発生します
映像研究部が学園祭用に撮影をするということで、とある廃墟に5人+巴先生で撮影に行きました
撮影していたところ、車が近づいてくるのに巴先生が気づきます
どうやら、若い男女が集まって何かいかがわしいことをしているに違いないと思い込んだ地元の名士が、いちゃもんをつけに来たようです
巴先生の指示で、まず女生徒3人がその場から離れることになりました
勝利ともう一人の男子生徒が機材の片付けを終え、階段を下りていると、とあるものを発見します
人間の首です
その後、手足、胴体がバラバラの状態で発見されます
この二つの事件の真相はいかに…?
ネタバレあり感想
ここからはネタバレありで感想を書いていきます
「たかが殺人じゃないか」未読の方はご注意ください
序盤の描写の意味
私がこの小説を読んで印象的だった場面は二つありますが、そのうちの一つが序盤の描写です
物語は冒頭の勝利の
「お前が犯人だ!」
というセリフから始まります
そのとき勝利は一人で部室にいましたが、探偵に憧れている勝利はなんとなくそのセリフとともに部室入口の扉を指さします
すると巴先生が入ってきて、
「ほう、私が犯人か」
と言います
何やらふざけたシーンから始まったな、と私は思いました
実際そのセリフから何か発展することはなく、部員たちも集まってきて雑談が始まります
この特に意味のなさそうな描写が、物語のラストで意味を持ちます
劇中で発生する2件の殺人事件の犯人は巴先生でした
これを踏まえて冒頭のシーンを振り返ると、最初に勝利は犯人を指さしていたことになります
私は巴先生が犯人だと判明してもそのことに気づいていなかったのですが、物語終盤の勝利のセリフでハッとしました
そもそも「たかが殺人じゃないか」は勝利が体験したことを元に書いた小説、という設定があります
勝利はありきたりの小説にしたくないという想いから、ある仕掛けを思いつきます
それが、
物語の最初に犯人を示す
というものです
だから冒頭で勝利が指さした先には巴先生がいたのです
この仕掛けが明かされたとき、
「なるほど!! そういうことだったのか!!」
と思わされました
最初の何気ない描写が物語後半で違う意味を持つ、という伏線回収の醍醐味を味わわせてもらいました
タイトルの意味
この小説のタイトル
「たかが殺人じゃないか」
少し物議を醸しそうなタイトルですよね
私も小説を買うときに
「なんでこんな軽い感じなんだろう?」
と思いました
タイトルの意味も物語中で明かされます
なぜこんな軽い感じになったかというと、
戦争が終わってまだ4年しか経ってないから
です
「たかが殺人じゃないか」
というのは、物語の登場人物が発するセリフから来ています
一人は被害者の地元の名士で、もう一人はその人を殺害した巴先生です
地元の名士は終戦当日に巴先生の妹を殺したことが理由でその4年後に巴先生に殺されるのですが、最初巴先生は名士を殺す気はありませんでした
事情を訊きたかっただけでした
しかし、その名士は、巴先生の妹を殺したことを悔やむどころか、
「たかが殺人じゃないか」
と言い放ちました
そして杖に仕込んでいた刀で巴先生に切りかかってきたため、返り討ちにしたのでした
4年前は戦争中で、殺人は日常茶飯事でした
そういった時代背景もあっての
「たかが殺人じゃないか」
というセリフ
数年前まで人を殺すのが当たり前だった人間なら、このような言葉が出てくるのもうなずけます
逆にこのセリフに違和感を覚えるということは、今私が生きている環境が平和だからだと思います
現在進行形で戦禍に苦しんでいる人ももちろんいますが、少なくとも私には遠い話です
これからも遠いままであってほしいです
何気ないセリフですが、今の時代を考えさせられました
まとめ
今日は小説「たかが殺人じゃないか」を紹介しました
戦後の混乱期を舞台にし、その時代ならではの価値観を反映した作品です
しかし物語の仕掛けは全く古臭くありません
いつの時代でも通用するような仕掛けで、読者を驚かせてくれます
機会があればぜひ読んでみてください!
今日も最後まで読んでいただいて、ありがとうございました!
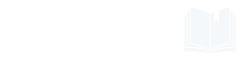
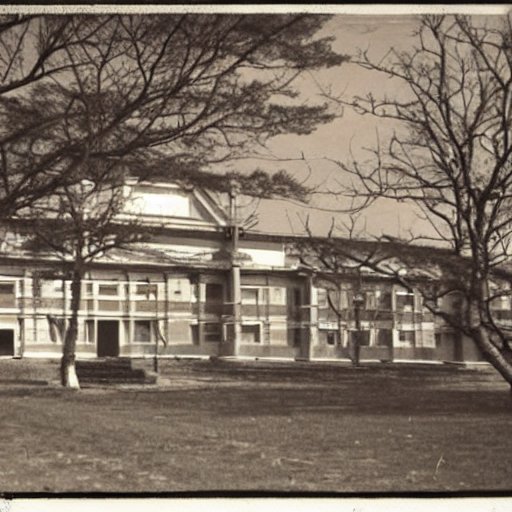


コメント