こんにちは!
今日は最近読んだ小説「神のロジック 次は誰の番ですか?」を紹介します
西沢保彦による作品で、書かれたのは2003年です
マモルという11歳の少年が、預けられた施設で同年代の少年少女と交流していきます
その施設は英語や数学が教えられるのに加えて、推理能力を鍛えられるような課題も与えられます
マモルは自分がなぜこの施設に預けられているか理解しておらず、周囲の子供たちに話を聞きながら自分の置かれている状況を把握しようとします
施設ではときどき不可解な事件も発生し、その謎を解きながらマモルは段々と真実に近づいていきます
終盤で明かされる真実は、読者の認識をひっくり返すような驚きの内容になっています
こんな人におすすめ
「神のロジック 次は誰の番ですか?」はこんな人におすすめです
- 伏線回収ものが好き
- 予想できない展開に驚かされたい
- 心理学が好き
あらすじ
あらすじを簡単に紹介します
主人公は11歳の少年のマモル
彼は元々神戸に住んでいましたが、今はとある施設に預けられています
その施設にはマモルを含めて六人の少年少女が預けられており、共同で生活しています
彼らはほぼ同年代ですが、足が悪くて車椅子生活の少年もいます
その少年と同じような状態の子供たちを受け入れるためか、マモルたちの部屋も病院のようにいたるところに手すりがついています
マモルはその施設に預けられた経緯をあまりよく覚えていないのですが、自分が両親と暮らしていた家から一度見知らぬ中年男女の家に預けられてから施設に入った記憶があります
この見知らぬ中年男女に心あたりのないマモルでしたが、他の子供たちに訊いてみたところ、みんなもマモルと同じように一旦両親の元から見知らぬ大人に預けられてから施設にきたようです
また、施設では英語と数学の勉強が日課として課される他、推理能力を鍛えるための課題も出されます
とある事件の状況と何人かの登場人物が設定されて、誰が犯人かを推理するという内容です
マモルは常日頃から、この施設は何なんだろう?という疑問を抱いており、周囲の子供たちにも話を聞きますが、みんな言うことはバラバラです
とある少年は秘密探偵養成施設、別の少年はヴァーチャルリアリティ、とある少女は前世の記憶を持つ特殊能力を備えた子供たちの研究施設だと言います
そんな施設での生活ですが、新しく子供を迎え入れることになって状況が一変します
既に入所している子供たちの様子がおかしくなり、みんな精神的に不安定になります
実際に新しい入所者が紹介されたときにも、マモルにはその姿が見えませんでした
このような不可解なことがあった翌日、事件が起こります
新しく入ってきた子供が失踪してしまったのです
施設内で見つけられなかったため、施設を管理している大人たちは外を探しに施設を留守にします
その間にマモルたちは、別の子供の死体を発見してしまいます
果たして、誰が凶行に及んだのか、この施設の正体は何なのか
予想できない真実が待っています
ネタバレあり感想
ここからはネタバレありで感想を書いていきます
未読の方はご注意ください
鮮やかな伏線回収
この作品の最大の仕掛けは、
「実はマモルたちは老人である」
ということにあると思います
11歳だと思い込んでいたマモルは、実は70歳を超える老人でした
ずっと見た目は老人のままだったのですが、自らを11歳だと思い込んで施設で生活していたのです
他の子供たちも同様です
これは物語の情景を読者の頭の中で補う小説ならではの仕掛けですね
マモルたちが実は老人であることを踏まえると、施設に関する描写に今までとは別の意味を見出せます
マモルたちの部屋に手すりが付いていることや、車椅子生活の登場人物がいたこと
マモルが施設に入る前に見知らぬ中年男女の家に預けられていたという記憶も、本当は自分の子供と一緒に暮らしていた記憶を忘れてしまっていたのです
また、英語や数学、推理能力を鍛える課題はボケ防止のためでした
他にも、施設で出される食事は味が薄くて柔らかいものばかりで、マモルたちは料理長が高齢だからではないかと考えていたのですが、それも本当は老人である自分たちの健康維持のためでした
このように、施設に関するあらゆる描写の本当の解釈が次々と明らかになっていきます
「そういうことだったのか!!」
と感心してしまうこと間違いなしです
人間の見てる世界
マモルたちがなぜ自分たちのことを少年少女だと思い込んでいたかというと、施設長であるシフォード博士が、人間の思い込みに関する研究をしていたからです
博士は家族から見捨てられた老人たちを施設に集め、彼らが思い込みの世界で生きられることを実証しようとしていました
老人の見た目は変えずに、周囲の人間が自分のことを本当の子供ように扱えば、次第に本人も自分のこと子供だと思い込むのではないか、という実験です
そして、自分のことを子供だと思い込んだ老人たちのコミュニティをどこまで広げていけるか、ということも試していました
博士は、本当は黒いものでも、自分以外の全員がそれは白だと言えば、自分もそれを白だと認識するはずだ、という仮説を持っています
この考え方を読んだとき、私は
「この例は極端だけど、普段の生活で真実ではないことを真実だと思い込んでしまうことって結構あるよなー」
と感じました
最近ホットな話題を挙げるなら、中国による日本産水産物禁輸措置でしょうか
日本政府が福島第一原発から放射性物質であるトリチウムを含んだ処理水を放流していることに対する制裁措置です
放流にあたって、トリチウムの濃度は科学的根拠に基づき、自然界に悪影響を与えない程度まで薄められています
しかし、中国はこの処理水を放流することに対して批判的です
現在中国はバブルが崩壊して経済成長が鈍化し、内政が不安定になりつつあるため、国民の負の感情を日本に向けることで中の問題から目をそらせようとしているのだと思います
さすがに中国の政府高官で、本気で処理水が自然界に影響を与えると信じている人はいないでしょう
しかし、一般の国民はそうではないかもしれません
本気で日本の水産物が危ないと信じている人もいると思いますし、なぜか水産物に限らず不買運動が広がりつつあります
このように思い込みによって、科学的見地に立って冷静に考えてみればおかしな行動も、人間はとってしまうことがあります
私自身も思い込みによって失敗したことは数えきれないくらいあります
特に大きな決断をするときには、自分は思い込みに囚われていないかを慎重に検討しながら行動しなければいけないなと思いました
まとめ
今日は小説「神のロジック 次は誰の番ですか?」を紹介しました
謎の施設に預けられたマモルたちに関する真実に、驚くこと間違いなしです
謎が謎を呼ぶ展開で、何気ない描写が後々伏線として活きてきます
機会があれば読んでみてください
今日も最後まで読んでいただいて、ありがとうございました!
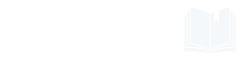



コメント